「職場であだ名はハラスメント?」
「からかいのつもりだった」なんて言葉では済まされない、じわじわと心を削る呼び方。
笑って流してきたけど、本当はずっと嫌だった…そんな経験、ありませんか?
この記事では、あだ名という名の「無自覚ハラスメントの正体」と、
あなたの「尊厳を守るための対処法」を、やさしく、でも率直にお伝えします。
【目次】
- 職場のあだ名は【どこからハラスメントになる?】基準を解説
- あだ名ハラスメントは違法?【職場での法的リスクとは】
- なぜ職場のあだ名がハラスメントになるのか?【心理的背景】
- 職場の【嫌なあだ名をやめさせたいとき】の対処法
- 企業が取るべきあだ名ハラスメント防止策とは?
- 職場での呼び方マナー【あだ名の代わりに使うべき】敬称とは
- 【まとめ】あだ名ハラスメントから心を守るためにできること
1. 職場のあだ名は【どこからハラスメントになる?】基準を解説

職場のあだ名は、「本人が不快に感じた時点」でハラスメントになり得ます。
どれほど親しみを込めたつもりであっても、
受け手の感情が優先されるのが現代の職場マナーです。
厚生労働省のマニュアルでは、「個の侵害もパワハラの一種」とされ、「名前を茶化す行為」は「精神的苦痛を与える可能性」があります。
冗談のつもりでも繰り返されると、知らぬ間にストレスの原因になることもあります。
- 容姿をからかうようなあだ名
- (例:「デブちゃん」「ハゲ」「チビ」など)
- 性格や特徴を揶揄する呼び方
- (例:「泣き虫」「KY」「トロい人」など)
- 年齢や性別を強調するもの
- (例:「ババア」「ジジイ」「女子力」)
- 過去の失敗を揶揄するもの
- (例:「ポカミス王」「伝説のミスメーカー」)
- 相手が否定しているのに使い続けるあだ名
- (例:「本人が嫌がっているが周囲がやめない」)
呼び方は「つけた側」ではなく「受けた側」の感じ方がすべてです。
「たかがあだ名」と軽視せず、相手の尊厳を守る意識を持つことが、信頼される社会人の基本姿勢です。
相手を「ちゃん付け」で呼ぶのはセクハラになるのでしょうか?ちゃん付けで呼ばれることに対して、下記のように人によってとらえ方が違うため、セクハラになる場合とならない場合があります。
2. あだ名ハラスメントは違法?【職場での法的リスクとは】
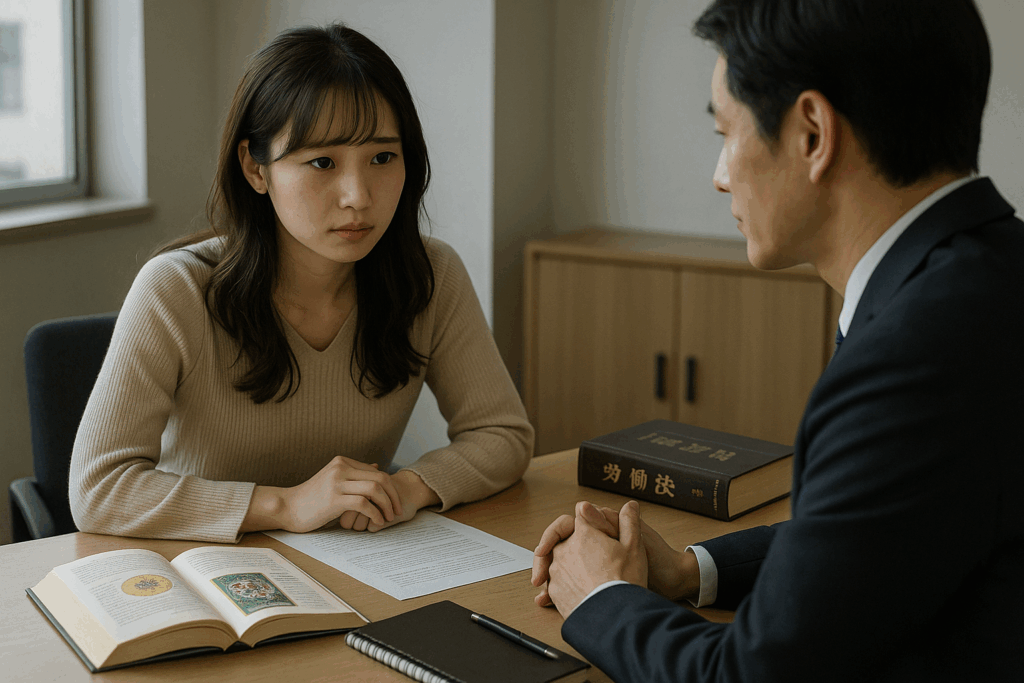
「あだ名による継続的な言動」が、「労働契約法やパワハラ防止法」に抵触する可能性があります。
たとえ軽い冗談のつもりでも、受け手が不快に感じ、それが繰り返される場合、法律上の責任が生じる恐れがあります。
「労働契約法第5条とパワハラ防止法」では、企業に労働者の安全配慮や「精神的苦痛の防止が義務づけ」られています。
呼ばれたくないあだ名を繰り返す行為は、精神的被害として損害賠償の対象となる可能性があります。
⑴ 呼ばれたくないあだ名(「デブ」「キモイ」など)を業務時間中に繰り返し使われ、本人が不眠症やうつ症状を発症しました。
最終的に休職に追い込まれ、労災として認定されたケースです。
⑵ 人事面談で「そのあだ名がつらい」と訴えたにもかかわらず、会社が対応せず放置した結果、企業が安全配慮義務違反として訴えられた例も。
「ただの冗談だった」は通用しません。
呼び方ひとつが法的リスクを生むこともある以上、企業も個人も、日頃から慎重な言動を心がけるべきです。
おススメ記事
3. なぜ職場のあだ名がハラスメントになるのか?【心理的背景】

あだ名は職場の人間関係における見えない「上下関係や差別意識」を強化し、「心理的なダメージを与える可能性」があります。
特に、本人の意志に反して使われるあだ名は、その人の尊厳や立場を脅かす要因になり得ます。
令和年労働安全衛生調査では、職場の人間関係にストレスを感じている人が54.2%。
「呼称やあだ名は心理的安全性に影響」し、差別意識を含む場合は「自己肯定感の低下や孤立を招く」こともあります。
上下関係のある職場でのあだ名は支配関係を強め、部下が断れず心理的に服従する状況を生む可能性があります。
- 「ポンコツ」「お局」など
- レッテル的なあだ名で笑いを取る風潮
- 「天然」「地味子」「陰キャ」など
- 性格や雰囲気を一方的に決めつける表現
- 「課長のお気に入り」など
- 嫉妬や偏見に基づくあだ名がいじめの温床になることも
呼び方は、その人の存在をどう扱うかの象徴です。
心理的安全性を保つには、相手の気持ちや立場を思いやる視点が欠かせません。
「冗談のつもり」が、誰かの心を傷つけていないか、一度立ち止まって考えてみることが大切です。
人間関係と自己肯定感UPに
➡外出せず3時間で履歴書に書ける資格がとれる!伝え方コミュニケーション検定
![]()
4. 職場の【嫌なあだ名をやめさせたいとき】の対処法

違和感を無視せず、「伝える」「相談する」「記録する」の3ステップで行動しましょう。
あなたの声は、あだ名を止めさせるだけでなく、自分自身を守るための大切な一歩です。
嫌なあだ名を我慢すると「心身に悪影響が出る」うえ、「周囲に誤解されて定着しやすく」なります。
早めに意思を伝えることが大切です。
やんわり伝える
「ちょっとその呼び方、実は昔から苦手で…」などと穏やかに切り出す。
相手に悪気がないことを前提にすると、受け入れてもらいやすくなる。
- 相談する
- 直属の上司、人事部門、または外部の総合労働相談コーナーへ相談する。
- 第三者が介入することで、冷静な解決に繋がるケースもあります。
- 記録を残す
いつ・どこで・誰に・どんなあだ名で呼ばれたかを記録する。
日時や自分の感情もあわせてメモに残し、証拠として備えておく。
- 同調してくれる味方を探す
- 「実は私もそう思ってた」と
- 共感してくれる同僚がいれば、相談時の心の支えになります。
「嫌だ」と感じたあなたの感情は正当で、「無視されていいものではありません」
あなたには、快適に働ける権利があります。
遠慮せず、安心して声を上げてください。
それは、あなた自身の未来を守る勇気ある行動です。
5. 企業が取るべきあだ名ハラスメント防止策とは?

あだ名ハラスメントは「企業文化の問題」でもあり、「個人の尊重と職場環境の健全性」を守るために、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。
労働施策総合推進法により、「すべての企業はパワーハラスメント防止措置」を講じる義務があります。
これには「あだ名による人格侵害」など、日常的で見過ごされがちな言動も含まれます。
職場内でこうした言動が常態化すると、被害者の離職、職場のモチベーション低下、社外からの評判悪化、最悪の場合は法的責任まで問われるリスクがあります。
- 社内ハラスメント研修の導入
- あだ名ハラスメントの事例を用いた研修で、社員の理解を深めることができます。
- 社内ポリシーへの明記と周知
- 就業規則や行動規範に「呼称に関する配慮」を明記し、全社員に定期的な周知を徹底する。
- 定期的な環境アンケートの実施
- 無記名でのアンケートを年1〜2回行い、潜在的なハラスメントの有無を把握。
- 管理職への特別研修
- 上司向けに、呼び方や声かけの注意点を学ぶマネジメント教育を行う。
- 相談窓口の設置と可視化
- 社内外の相談窓口を複数設け、従業員が安心して利用できる体制を整備。
あだ名は軽視できないハラスメントの入り口です。
企業は風通しのよい職場環境を守るために、積極的かつ具体的な対策が求められています。
6. 職場での呼び方マナー【あだ名の代わりに使うべき】敬称とは

基本は「○○さん」「○○主任」など、敬称や役職名を用いた呼び方を心がけましょう。
呼び方ひとつで、人間関係の信頼性と職場の空気は大きく変わります。
厚生労働省のハラスメントマニュアルでも、「呼称や言葉遣い」は「ハラスメント防止の基本」として扱われています。
親しみを込めたつもりのあだ名も、受け手がどう感じるかによっては一線を越える可能性があります。
とくに「上下関係のある職場」では、呼び方の選択が「無意識の圧力や差別意識」につながることもあるため注意が必要です。
また、職場での適切な呼称は、社内外問わず企業イメージの一端を担うという視点も重要です。
- 初対面や社外の方には
- 「○○様」「○○先生」と敬意を込めた呼称を使うことで、丁寧な印象を与えられる。
- チーム内では
- 「○○さん」で統一することで、公平で安心感のある職場づくりにつながる。
- 部下や後輩には
- あだ名ではなく「○○さん」「○○くん」と呼ぶことで、信頼と尊重のバランスが保たれる。
- 本人の希望がある場合
- (例:「ニックネームで呼んでください」)
- でも、職場全体の空気感を見て慎重に判断する。
- また、呼び方に違和感がある場合には、
- 「どう呼んだらいいですか?」
- と相手に確認する姿勢が信頼を築く鍵となる。
呼称は相手への敬意の表れです。
「なんとなく」で選ぶのではなく、状況や相手の気持ちを汲み取った上で言葉を選ぶことで、職場に安心と信頼の空気が育ちます。
7. 【まとめ】あだ名ハラスメントから心を守るためにできること

嫌なあだ名に違和感を覚えたら我慢せず伝えてOK。
それはあなたを守る大切な感覚です。
ひとりで抱えず、「公的な支援や対処法を活用」しながら、安心して働ける環境を選んでください。

